
■人生の指標
2015年2月の「ドファララ門」トーク&ライブから3年が過ぎた。トークで共演した音楽評論家の相倉久人さんがその夏に急逝。半世紀以上、人生の指標となった人だった。
「僕が1969年にフリー・ジャズを始めたとき、根底には相倉さんの言葉、『やりたいことを思い切りやればいいんだよ』があったんです」
60年代半ばまでは主流派のジャズメン。68年に大病を患ったことがフリーへ変遷したきっかけとも言われるが、一夜にして成ったわけではない。
「どう考えても、フリーの出発点は相倉さん。誰でも認める正当派を嫌がる人で、前衛派のセシル・テイラー(米ジャズ・ピアニスト)とか、みんなが遠ざけてきたものを、『自分の好きなことをやればいい。それがジャズのいいところです』と教えてくれた。後年にセシルとデュオができたのも、そのおかげです」
一方、強制的なことはまったく言わなかった。
「音楽について、ああしろこうしろはなくて。ただ、『僕は音楽を他人より深く聴くことはできるよ』と。だからいろいろ音楽のことを聞きたくて、阿佐ヶ谷の喫茶店で毎週、みんなで囲んで。自然と音を追求するようにもなっていきました」
■一柳慧、オノ・ヨーコ 前衛音楽家と出会い
一柳慧(作曲家、ピアニスト)ら、前衛音楽家とのつながりもできた。
「一柳さんは草月ホールでよく演奏していて、バイオリンを持った女性がグランド・ピアノに潜り込んだと思ったら、それがオノ・ヨーコさん。とにかく面白くてすごい人のことをたくさん教えてくれて、それが僕の音楽に反映されていった」
唐十郎(劇作家)との出会いも。
「ピットイン(新宿のジャズ・スポット)に、唐さんが夜中に芝居をしに来ていて。相倉さんが『君は、芝居に合わせて勝手にピアノを弾いちゃいなさい』と。それが唐さんの紅テント(67年、新宿・花園神社)の演奏にまで広がった。その翌年に僕は体調を崩し、69年にフリー化するんですが、そのときにはまず“相倉さんに見てもらいたい”気持ちが強かった」
■筒井康隆と結成“冷し中華愛好会”
一連の輪の中には筒井康隆(作家)もいた。
「相倉さんがピットインの原稿を筒井さんにお願いしていた縁で、僕を紹介してくれた。僕が復帰したら筒井さんが観に来てくださり、フリー化を喜んでもらえて。毎週ライブが終われば飲み歩いて。ずっと筒井さんのファンだったからうれしくて。“全日本冷し中華愛好会”なんてのもやった。騒ぐ僕らを相倉さんは遠くから見ていてくれた」
その恩師に捧げるライブ。演じるメンバーは3年前と同じだ。
「ドラムの堀越(彰)君は実に素直で、ここで入ってきてほしいというところで、決まって入ってきてくれる。わざとずらしてくる人もいるんだけど、彼にはない。真っ向勝負してくれます」
サックスは菊地成孔。
「中学生のときに“山下洋輔ごっこ”をやっていたという変わり者。出会った時からフリー・ジャズのガボガボ・ゲボゲボができた。何事も詳しく調べるのが大好きで、僕が知らないジャンルの音楽もやっていて、若い人にも影響力があるね」
トークには菊地と、建築家、建築史家の藤森照信氏(江戸東京博物館館長)も出演する。自身のルーツを語るうえで、かけがえのない恩人だ。
「五大監獄を設計した山下啓次郎の子孫は誰かと藤森先生が調べていらっしゃって、それがジャズの山下だという話になった。祖父の啓次郎が東京駅を建てた辰野金吾の弟子とか様々なことを教えていただいた。山下家のルーツをたどった拙著『ドバラダ門』が生まれ出たのも先生のおかげ。一方で赤瀬川原平さんや南伸坊さんと“路上観察学会”を作っていた、面白人間なところもすごい」
近年、祖父が設計した奈良少年刑務所の保存が決まったときにも、その存在は大きかった。
「僕は“奈良少年刑務所を宝に思う会”の会長で、国に保存を決めてもらうにはどうすればよいのかと藤森先生に相談したら、『谷垣さんに会うのがいい』と。自民党の谷垣禎一さんの事務所に一緒にうかがいました。うれしかったですね」
その藤森氏に菊地が挑むトークは、さながら異種格闘技戦の様相を見せる。
「菊地が藤森先生のことを調べ尽くして挑むんでしょう。まだ知らない面が見えてくるのではないかと楽しみ。菊地をどうけしかけようかなあ」
いたずらっぽく笑う表情はいくつになっても変わらない。恩師の「やりたいことをやりなさい」という教えを胸に、今回のトーク&ライブも思いっきり楽しむつもりだ。(ペン・秋谷哲 カメラ・斎藤良雄)
【どんなタイプでも解決できる】みたいに言ってるのが
ちょっと【インチキくさい】感じがするのよね
よく公式サイトとかに出ているモニターさんって
成功したから、代表例として出演しているわけで・・・
全員が【必ず】成功するとは限らないよね。
かといって
実践者のリアルな口コミを読んでると
かなり高い効果を実感できるみたいだよね。
信じて、試してみようかな

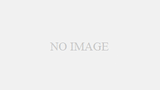
コメント