
高橋みなみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「高橋みなみのこれから、何する?」。3月27日(火)の放送には、朝日新聞社の田中志織さんが登場。新聞作りの裏側について教えてもらいました。
現在、田中さんは“マーケティング本部マーケティング部部長”という肩書きですが、入社当時には記者も経験。最初は“サツ(警察)まわり”からスタートし、市政や県政、高校野球などを担当しながら記者のイロハを学んだそうです。
たかみなは“サツまわり”という言葉を聞き、「ドラマで聞いたことがある!」と興奮気味の様子です。しかし、田中さんにとっては忘れたい言葉らしく「(記者時代は)ツラい思い出しかありません……」とポツリ。
そんな田中さんが考える新聞の魅力、それは「守備範囲が広いこと」「深く知れること」「世界が広がること」の3つ。その日の動きを伝えるのが大きな役割の新聞には、政治や経済だけでなく、料理レシピやお悩み相談、イベント情報などさまざまな記事が掲載されています。それだけに、新聞をめくっていると思わぬ情報に出会えたり、いろいろな人のドラマを垣間見ることができたりして世界が広がると田中さんは言います。
たかみなが気になっているのは、新聞の作り方。毎日休むことなく届く新聞はどうやって作られているのか、田中さんに聞いてみると……まずは記者が取材して原稿を書き、それをデスクと呼ばれる責任者がチェックします。情報不足の記事は再取材をして原稿をまとめ、その後はレイアウトや見出しを考える編集センターと、文章の内容を確認する校閲センターへ。そこで新聞の形に編集され、印刷所、販売所にわたり読者のもとへと届けられるそうです。
ちなみに、朝日新聞社は海外にも拠点があり、記者数は国内外併せて2,000人以上。1日平均250ページの文庫本7冊分ぐらいの記事が集まり、その中から厳選しているとか。
そして、ネタ決めは毎日夕方と夜にデスク会で行われ、そこで朝刊のおおよそのメニューが決定します。その会議では各部の編集局員や当番編集長、デスクなどが参加し、一面にふさわしいネタをプレゼン。最終的に合議制で決まるそうです。ちなみに、ドラマなどでよく観ることのある深夜に記事を差し替えるシーン……それは実際よくあることで、締め切りギリギリまでせめぎ合いは続くようです。
新聞作りは時間との戦い。それだけに、「寝ているときにも(締め切りが)夢で出てきそうですね……」とたかみながつぶやくと、田中さんは「編集者のときに紙面が真っ白の夢を見たことがあります。それは編集者なら誰でも見る夢ですね……」とツラい編集者あるあるを明かしてくれました。
また、情報満載の新聞記事をより面白く、効率的に読むためのポイントとして田中さんが教えてくれたのは、まずは見出しを読むこと。その後に第一段落、記者用語でいうリード(前文)へ。そこには記事のエッセンスが詰まっており、リードを読んでもわからない記事は下手な記事なんだとか。
来年で創刊140周年を迎える朝日新聞。今やネットの時代と言われていますが、速報性は劣るとしても、ニュースの本質をいかに読者に伝えられるか、さらには読者の考えるヒントになるような紙面作りを心がけていると田中さんは言います。最近では女性向けのコンテンツも豊富になり、「ぜひ自分に合ったコンテンツを見つけてもらえれば」と田中さんは話していました。
口コミとかで
いろいろな意見の書込みがあるけど
実際は【効果なし】なの?
何でも個人差はあるから仕方ないんですけどね
ほとんど全員が【効果あり】みたいに書かれてるのが
ちょっと怪しい気もすんですけど・・・
でもちょっと期待もしてしまいますよね
やってみようか・・・悩むな~

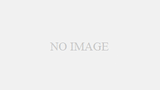
コメント