
文/田中昭三
東京の上野公園に立つ西郷隆盛さんの銅像に、久しぶりに立ち寄ったときのこと。いままでじっくり見たことがないので、銅像のまわりをゆっくり一周してみた。
向かって右横から見ていると、足に履いた草鞋(ぞうり)が気になった。鼻緒の位置が足の中ほどにあり、草履を深く履いていないようなのだ。でも、そんなだらしない姿を、銅像にするだろうか。
そこで思い出した。これが「足半(あしなか)」という草履なのだ。
足半草履とは、通常の草履の半分くらいの長さで、踵(かかと)の部分がない。実業家にして民俗学者だった渋沢敬三(1896~1963)が、戦前各地を歩いて300点近く蒐集(しゅうしゅう)していた。
こんな草履はいつごろから履かれるようになったのか。視覚的に確かな資料は永仁(えいにん)元年(1293)作の『蒙古襲来絵詞(もうこしゅうらいえことば)』。そこには足半を履いた武士が描かれている。ということは、足半が作られたのはこの時代以前の平安時代末までさかのぼりそうだ。
戦国時代の雄・織田信長は普段から足半を腰につけていた。越前の覇者朝倉一族との合戦で、一人の家来は奮闘のあまり草履が脱げてしまった。それでも相手の武将の首をとり信長に持参。そのとき信長は腰の足半を褒美に与えたという。
足半は江戸時代末までごく普通に使われていた。足を踏ん張って作業をする農民や船乗り、さらには飛脚などに重宝された。いまは長良川の鵜飼いの鵜匠が自作の足半を履いている。
実はいまも足半屋という店があり、この草履を販売している。その店の話によれば、足を鍛えたいスポーツマンや腰痛・肩こりに悩む人などにお勧めという。
とかく生活が便利になり身体が衰えている現代人。西郷どんも愛用していた(かもしれない)先人の知恵が生んだ便利な履き物を、見直してはどうだろうか。
文/田中昭三
京都大学文学部卒。編集者を経てフリーに。日本の伝統文化の取材・執筆にあたる。『サライの「日本庭園」完全ガイド』(小学館)、『入江泰吉と歩く大和路仏像巡礼』(ウエッジ)、『江戸東京の庭園散歩』(JTBパブリッシング)ほか。
ネットの評判や噂って
実際のところどうなんだろう?
正直、ノウハウに興味あるから気になります。
こんなに簡単に効果がでるんなら
すぐにでもやってみたい気がするんですよね。
評判や口コミどおりに効果あるなら
嬉しいけど・・・。

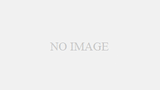
コメント